シロップを売りたい、でも何をすればいいの?
「家族のために作った自家製シロップを販売してみたい」
「でも保健所の申請って、どうすればいいの?」
「自家製のシロップをネットで販売してみたいけど、まず何をすればいいの?」
そんな疑問を抱いたことはありませんか?
実は、私たち自身もまったく同じ状況からスタートしました。インターネットで調べても「シロップ製造は○○業に当たる」なんて明確な答えは見つかりません。
調べれば調べるほど、「お菓子は“菓子製造業”」「飲み物は“清涼飲料水製造業”」と書いてあるのに、肝心のシロップについてはどこにも書かれていない…。
情報が錯綜するなか、「そもそも保健所の許可って本当に必要?」「届出だけでいいって聞いたけど…」と混乱する人も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんなモヤモヤを抱えたあなたに向けて、
実際に保健所に問い合わせ・訪問し、許可を取得するまでのリアルな体験談をもとに、以下の3点をわかりやすく解説していきます。所立ち合いによる許可が必要ものなのか、それとも保健所に申請書を提出するだけでいいのか、が決まってきます。
この記事でわかること
- ジンジャーシロップの製造は、何の業種に分類されるのか?
- 保健所の申請方法と必要書類
- 許可が不要なケースと、必要になるケースの違い
この3点について詳しく解説しています。
市販の情報に振り回される前に、実体験に基づいた確かな情報を知って、一歩ずつ進んでいきましょう。
次章では、まず「食品の販売に必要な許可とは?」という根本の仕組みからわかりやすく説明していきます。
食品を販売するには許可が必要?—法律の基本を解説

ジンジャーシロップに限らず、何かを「食品として製造・販売」しようと思った時、避けて通れないのが「保健所の許可」です。
なぜ許可が必要なのかというと、それは日本における食品安全の根幹を支えている参考リンク食品衛生法(しょくひんえいせいほう)という法律に基づいているからです。
食品衛生法ってなに?
食品衛生法の目的は明確です。
「食品の安全性を確保し、国民の健康を守ること」
厚生労働省が管轄しており、食品の製造・加工・販売などに関わるすべての人が対象になります。
つまり、趣味や副業レベルでも「お金をもらって売る」のであれば、一定のルールを守らなければいけないのです。
許可が必要な業種って?
食品衛生法では、食品のリスクに応じて 「営業許可が必要な業種(全32業種)」 を定めています。
たとえば以下のようなものがあります:
- 飲食店営業
- 菓子製造業
- 清涼飲料水製造業
- そうざい製造業
- 食肉処理業 など
これらに該当する場合、保健所で設備確認や講習などを受けた上で「営業許可」を取得しなければ販売ができません。
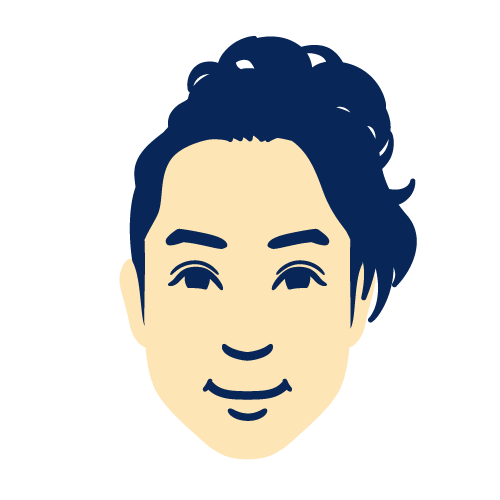
それ以外は「届出」でOK?
はい、一部の低リスクな業種については「届出制度」が導入されています。
たとえば以下のようなケースでは、営業許可は不要でも製造場所・業種・責任者などを保健所に届け出る義務があります。
- 野菜や果物の販売
- 加工品のラッピング作業
- 冷蔵保存が前提の調味料など
ジンジャーシロップはどれに当てはまるの?
…というところで、誰もが立ち止まるのがここ。
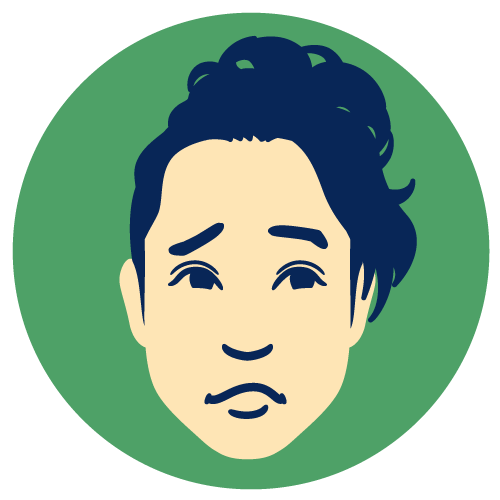
「じゃあ、ジンジャーシロップってどの業種に当たるの?」
という疑問です。
実は、この答えが非常にあいまいで、ネット検索では明確な情報にたどり着けないのが現状です。
この後の章では、私たちが実際に保健所へ問い合わせ、複数の自治体から回答を得た結果を詳しくご紹介していきます。
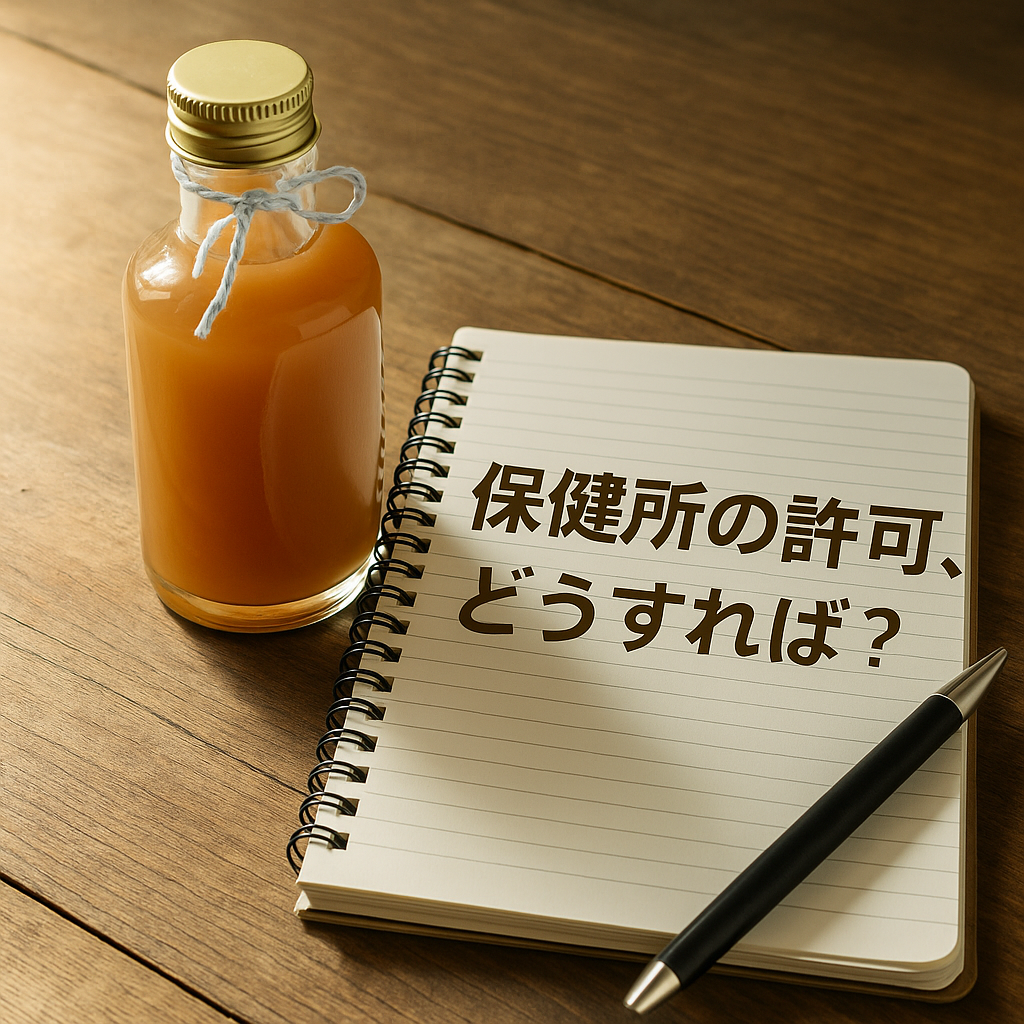

コメント